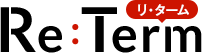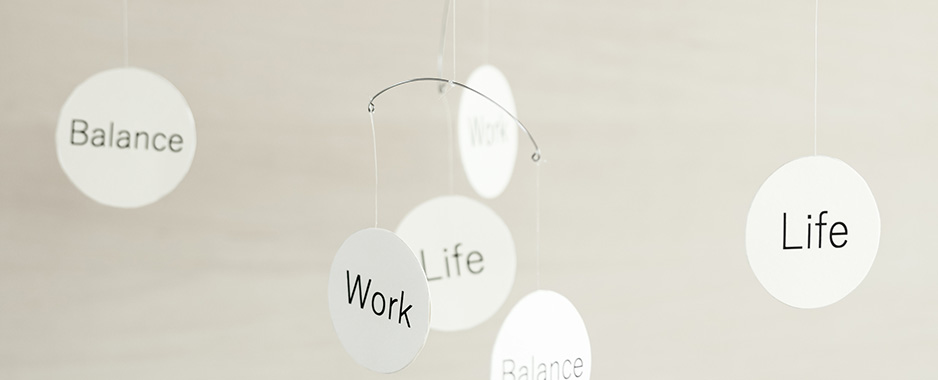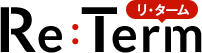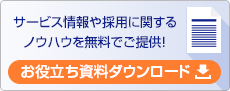ワークライフバランスは多様化する働き方や社会問題に対する解決策の1つとして注目されており、日本では内閣府が推進している政策でもあります。
しかし、ワークライフバランスを導入していない企業にしてみれば、どのような取り組みをすることがワークライフバランスにつながるのか判断しづらいでしょう。
そこで今回は、ワークライフバランスの意味やメリット、実際に会社が取り組んだ事例などについて解説します。
ワークライフバランスの意味と定義
ワークライフバランスとは、仕事と生活のバランスが取れた状態であり、その状態で得られる相乗効果や好循環を目的とする取り組みや考え方を指します。
現在の日本社会では、安定した仕事に就けず経済的に自立できない、仕事に追われ心身の疲労が大きい、仕事と子育て・老親の介護の両立に悩むなど、仕事と生活に関する問題を抱える人が多くいます。
この状況を解決する方法としてワークライフバランスは注目されており、働き甲斐のある個人を尊重した仕事の実現に取り組みつつ、育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった生活面のクオリティを上げることを目指します。
内閣府も「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会を実現するため、ワークライフバランスを会社が導入することを推奨する」としています。
ワークライフバランスのよくある誤解
ワークライフバランスのよくある誤解に、「ワークライフバランスは仕事よりも個人の生活を充実させること」という解釈があります。この解釈は本来の意味とは異なるものとされており、「生活を充実させることで仕事へのモチベーションが高まる、反対に仕事の成果や効率が向上すれば生活のクオリティを上げることが可能になる」というのがワークライフバランスの基本的な考え方になります。
また、ワークライフバランスにおいて時間配分や導入方法に関することは、画一的に決まっているわけではありません。「仕事と生活を時間できっちりと分ける」、「すべての業務をテレワークに切り替える」というような画一的な方法ではなく、時と場合によって柔軟に対応できるようにすることも大切です。
ワークライフバランスを推進することで会社が得られるメリット
ワークライフバランスを推進することで会社が得られるメリットは複数ありますが、代表的なメリットは次の3つになります。
- 会社のアピールポイントになる
- 優秀な人材の流出を防げる
- 従業員のモチベーションが向上する
ワークライフバランスを推進しているということは「働きやすい会社」としてイメージアップにつながり、人材募集の際に、就職活動中の学生や転職活動を検討している方へのアピールポイントになります。
また、ワークライフバランスを推進することで優秀な人材の流出を防げます。たとえば、出産や育児に関する制度を導入すれば、出産・育児を理由とする女性従業員の退職を防ぐことが期待できます。
ほかにも、ワークライフバランスの導入により生活が充実することで、従業員のモチベーションが向上する可能性があります。従業員のモチベーションが向上すれば会社全体の生産性や業績の向上、労働時間の削減による人件費や交通費などのコスト削減、従業員の健康維持など様々な面で効果を期待できます。
ワークライフバランスによって従業員が得られるメリット
会社にメリットがあるように、ワークライフバランスを推進することで従業員も次のようなメリットが得られます。
- プライベートと仕事が両立しやすくなる
- プライベートな時間が確保できる
- スキルアップや資格習得にチャレンジできる
総務省統計局が発表した「平成29年就業構造基本調査」によると、過去1年間に介護・看護のために離職した方は年間99,000人もいます。65歳以上の高齢者は2020年9月時点で3617万人と過去最多で、介護をしながら働く人の数は年々増加すると考えられます。
ワークライフバランスを推進することで、介護や子育てといった従業員のプライベートと仕事の両立がしやすくなり、退職を防ぐ効果が期待できます。
また、仕事の効率化に成功すれば、従業員はプライベートな時間を確保できます。自分で時間をコントロールできれば、休暇を家族と過ごせるようになり、仕事へのモチベーションの向上につながります。
ほかにも、従業員のスキルアップや自己学習、資格習得などにチャレンジする時間を作ることも可能になるでしょう。
ワークライフバランスの実現に必要なステップ

ワークライフバランスを導入するには、経営トップがワークライフバランスの取り組みを本気でおこなうと発信することが必要です。社内報や会社のホームページなどで、生活と仕事の両方を充実させることの重要性を強調しないと、従業員の意識は変わりません。
次に実働部隊となる担当者や担当部署を配置し、会社の抱えている問題や従業員の意識などを、コミュニケーションを取りながら調査します。そして、調査した情報に基づいて導入の目的と目標を定め、導入計画を立案したら、実行に移します。
実行に移しただけでは、ワークライフバランスの実現とはなりません。ワークライフバランスが定着するには達成状況の評価分析をおこない、問題点を改善し、ワークライフバランスを習慣化させていくことが重要になります。
ワークライフバランスを導入する会社の取り組み事例
ワークライフバランスの具体的な取り組みは次の5つになります。
- 休暇の取得促進
- 労働時間の柔軟化
- 多様な勤務スタイルの導入
- 残業時間の削減
- 福利厚生サービスの充実
どのような形で導入されたのか、それぞれの取り組み事例を解説します。
休暇の取得促進
休暇の取得促進とは、育児休暇や介護休暇などを取得しやすくするようにして、制度の内容を理解し、きちんと運用できる形に整えることです。
実際の会社の事例としては、ダブルアサインメント(仕事の2人体制)の導入があります。1つの仕事を複数人で分担すれば急な欠員が生じても誰かが常に代われるため、「子どもが急に熱を出してしまった」といったトラブルが発生しても休暇を取りやすくなります。
また、仕事内容によっては1つの業務を複数人で分担することで効率が上がり、労働時間を短縮できる可能性もあります。
労働時間の柔軟化
労働時間の柔軟化とは、従業員に何かしらの事情があっても仕事ができるように、時短勤務やフレックスタイム制などを導入して労働時間を固定しないことです。
実際の会社の事例としては、子どもと夕飯を食べたいという従業員の声に対して、子どもが小学校を卒業するまでの間は育児短時間勤務を可能とした例があります。
ほかにも、家庭の事情に合わせた「短縮労働時間制度」や「選べる出勤時間制度」などを実施したことで労働時間の柔軟化に成功しています。
多様な勤務スタイルの導入
従業員の希望や事情に沿った勤務スタイルを実現できるように、在宅勤務やテレワーク、地域限定社員制度といった多様な勤務スタイルを導入することも代表的な取り組み事例の1つです。
実際の会社の事例としては、家族の通院のサポートなど、従業員の個別事情に応じて出社よりもテレワークを推奨した例があります。働き方を選べることで、従業員の働きやすさが向上し、業務への支障を抑制できます。
残業時間の削減
残業時間の削減とは、長時間労働を抑制するために残業申告制度、ノー残業デー、残業免除制度、残業時間の事前申請義務化、業務フローの見直しなどを導入することです。
実際の会社の事例としては、「有給休暇取得日数20日(100%)・平均月間残業時間20時間以下」という目標を達成した部門に賞与を加算するという取り組みを導入したところ、従業員の満足度が大幅に向上し、働きやすい職場へと変化しました。
反対に、長時間残業が発生した部門にはペナルティを課すようにしたことで、結果として残業時間の削減につながった例があります。
福利厚生サービスの充実
従業員の仕事へのモチベーションや効率を向上させるために、会社内に託児所の導入、家事代行・ベビーシッターの利用料負担など、福利厚生サービスを充実させることもワークライフバランスの向上につながります。
実際の会社の事例としては、認可保育園と認可外保育園の保育料差額を全額負担する「認可外保育園補助」制度を設立した例があります。
自治体や所得によって保育料は異なりますが、たとえば東京都千代田区の場合は認可保育園の月額保育料が最大57,500円に対して、認証保育園は平均70,000~78,000円が必要になり、認可外保育園だとさらに高額になります。
この保育料差額を会社が負担したことで従業員の負担は軽減され、仕事へのモチベーションがアップすることも期待できます。
ワークライフバランスは多くの会社が実践し効果を上げている

ワークライフバランスは仕事と生活のバランスが取れた状態を目指す取り組みのことで、導入すると従業員のモチベーションや成果の向上などが期待できます。
内閣府が2007年から推進している政策でもあり、多くの会社が導入し、効果があったと回答しています。
ただし、すでに実践している会社の事例をそのまま導入しても正しい効果が出るとは限りません。自社の課題や問題点を明確にして、適切な解決策となる取り組みを導入することが大事になるでしょう。
【参考文献】